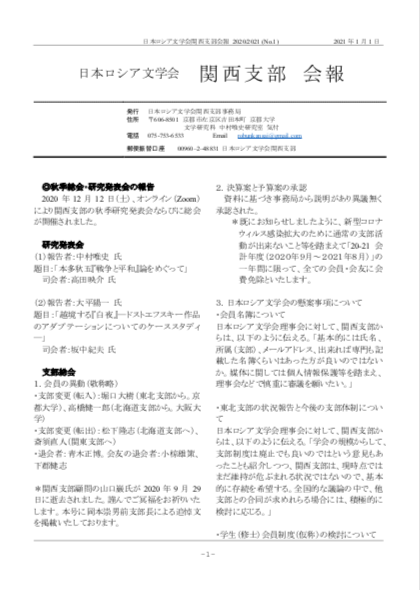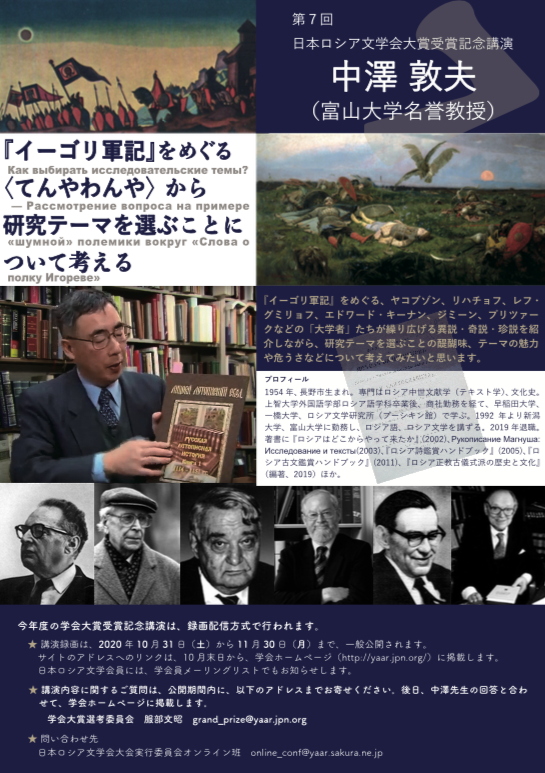学会からのお知らせ Мероприятия ЯАР
カテゴリ:広報委員会
枠を広げて:札幌での第66回大会を振り返って
望月哲男会長の「枠を広げて:札幌での第66回大会を振り返って」を掲載しました。
広報委員会
広報委員会
ミハイル・カラシク (Mikhail Karasik)氏特別講演
特別講演のお知らせ
ミハイル・カラシク (Mikhail Karasik)氏
(アーティスト、作家、評論家:サンクト・ペテルブルグ在住)
建築、100年の神話
―― 構成主義 / 新古典主義論争 ――
"Архитектурный миф столетия. Спор конструктивизма с неоклассикой"
日時:2016年11月11日(金)17:00−18:30
会場:東京大学文学部(本郷キャンパス)3号館7階 スラヴ文学演習室
The University of Tokyo, Faculty of Letters cor. 3, the 7th floor
所在地:〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
交通:地下鉄丸ノ内線・大江戸線「本郷3丁目」、南北線「東大前」などから徒歩10分
Metro: “Hongo 3 cho-me” or “Todai-mae”
* 予約不要。専門的関心をお持ちの方のご来聴を歓迎します。講演はロシア語日本語で行われます。No reservation needed. In Russian only.
講演内容
そのほとんどが実現しなかった神話的存在にもかかわらず、20世紀のソ連芸術を考えるうえで重要な意味を持っている「文化宮殿プロジェクト」について、自身の芸術創作実践の紹介も交えつつ、講演を行う。
研究書著作『ソヴィエト文化宮殿:建築プロジェクトのコンクール』、『ソ連版バベルの塔』
美術カタログ『レニングラードの構成主義建築』、『ヒデケリへのオマージュ』
*ラザリ・ヒデケリ(ロシア・アヴァンギャルドの画家、デザイナー、建築家。)
Lazar Khidekel: an artist, designer, visionary architect and theoretician, who is noted for realizing the abstract, avant-garde Suprematist movement through architecture.
В этой лекции Михаил Карасик будет рассказать об одном важнейших советских художественных проектов ХХ века −− строительстве Дворца Советов, который не был реализован практически, но реализовался как архитектурный миф. По этой теме напишаны им две работы: "Дворец Советов: конкурс проектов" и "Вавилонская башня СССР", а в качестве контраста еще два альбома: "Ленинградский архитектурный конструктивизм" и "Оммаж Хидекелю".
主催・問い合わせ先 東京大学文学部スラヴ語スラヴ文学・現代文芸論研究室 電話03-5841-3847(スラヴ)
講師のプロフィール
ミハイル・カラシク Mikhail Karasik(1953年レニングラード生まれ)
サンクト・ペテルブルグ在住のアーティスト。アーティスツ・ブックの分野におけるロシアの第一人者として知られるほか,1995年にアンナ・アフマートワ博物館で開催された《ハルムス・フェスティヴァル》をはじめとするブックデザインをめぐる数多くの展覧会のキュレーター,図録の編著者として国際的に活躍。作品はロシア美術館,トレチャコフ美術館,ポンピドゥー・センター,メトロポリタン美術館などの美術館,図書館に所蔵されている。
---
主要展覧会
■ 1990 − Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, Ленинград;
■ 1992 − Выставочный центр ?У книгоиздателя И. Д. Сытина?, Union Gallery, Москва;
■ 1993 − Музей Гуттенберга, Майнц;
■ 1993 − Центральный дом художника, Москва;
■ 1994 − Кабинет эстампов. Музей изобразительных искусств, Женева;
■ 1995 − Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Санкт-Петербург;
■ 1995 − Ярославский художественный музей, Ярославль;
■ 1997 − Государственный Эрмитаж. Научная библиотека, Санкт-Петербург;
■ 1998 − Саксонская государственная библиотека, Дрезден;
■ 1998 − Музей искусств, Чикаго;
■ 2001 − Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва;
■ 2003 − Государственный Русский музей, Санкт-Петербург;
■ 2004 − Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Екатеринбург;
■ 2007 − Галерея Anna Nova, Санкт-Петербург.
北海道大学大学院文学研究科 准教授の公募のお知らせ
北海道大学大学院文学研究科 准教授の公募のお知らせ
北海道大学大学院文学研究科では、「ロシア語学」の分野で准教授1名(採用日:平成29年4月1日)を公募しています。
詳細については、下記の北海道大学ホームページをご覧下さい。
以上
公開シンポジウム「セルボクロアチア語の在りし場所」のお知らせ
7月17日(日)、京都大学文学部新館第7講義室で、標記の公開シンポジウムを開催します(14:15開場、使用言語:英語、講師:ボヤン・ベリッチ氏(ワシントン大学講師)、野町素己氏(北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター准教授))。
詳しくは添付のチラシをご覧ください。皆様のご来場をお待ちしています。シンポジウム7-17.pdf
詳しくは添付のチラシをご覧ください。皆様のご来場をお待ちしています。シンポジウム7-17.pdf
特別講演 望月哲男氏「ドストエフスキーと古儀式派」
特別講演のお知らせ
望月哲男氏
(ロシア文学者・北海道大学名誉教授・日本ロシア文学会会長)
ドストエフスキーと古儀式派
――『カラマーゾフの兄弟』の教会裁判論を入り口に――
望月哲男氏
(ロシア文学者・北海道大学名誉教授・日本ロシア文学会会長)
ドストエフスキーと古儀式派
――『カラマーゾフの兄弟』の教会裁判論を入り口に――

コメンテーター:亀山郁夫(名古屋外国語大学学長)
司会:沼野充義(東京大学教授)
日時:2016年5月13日(金) 16:30-18:30(開場16:00)
場所:東京大学本郷キャンパス内 山上会館 2F大会議室(定員120名)
交通:地下鉄丸ノ内線・大江戸線「本郷3丁目」、南北線「東大前」、千代田線「根津」などから徒歩10-12分。
無料・事前予約。専門的関心をお持ちの方のご来聴を歓迎します。予約は不要ですが、満席の場合は立見をお願いすることもありますので、予めご了承ください。
詳細HP: http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~slav/04event/lecture.html
この3月で長年の勤めを終え、多大な功績を残して北大スラブ研究センターを退任された望月哲男先生の記念最終講義は、3月末に札幌で盛大に行われました。しかし、北海道まで行くことができず、講義を聞けなかったため残念がっている人たちが東京近辺にたくさんいます。
そこで、別途東京で機会を設けるため、望月氏の母校で特別講演を開催する運びとなりました。終了後は望月さんを囲んで懇親会を行いますので、心行くまでご歓談いただければと思います。皆様のご来場をお待ちしております。
なお、講演は予約不要で、どなたでも自由に先着順に入場していただけますが、万一、満席の場合は立見をお願いする場合もありますので、予めご了承いただければ幸いです。
懇親会につきましては、当日参加も席に余裕のある限り受け付けますが、できるだけ事前に予約をお願いします。
懇親会
講演終了後 午後7時-- Bistro Kouzo (ビストロ・コウゾウ)
文京区湯島4-6-17(講演会場から徒歩10分)、電話050-7300-4250
会費6000円(非常勤職・博士課程の方4000円、修士・学部学生の方2000円)
http://r.gnavi.co.jp/6v50yz8x0000/map/
予約は専用メールアドレス:slav.lecture■gmail.comまで(■はアットマーク)
講演趣旨(講師より)
『カラマーゾフの兄弟』の1部2編5章に登場する教会裁判論は、国家と教会の包摂関係や役割分担にかかわる議論として同時代性を持つと同時に、重要なテーマ提示機能を担っていると思われます。それはまず宗教的共同体の本質とは何か、教会と社会のかかわりはどうあるべきかという、作品の中心的関心に通じています。また同じく作品に通底する裁きのテーマ、包摂と排除のテーマ、さらに許しや寛容の問題とも関係しているように見えます。ではこの話題は、同じくロシア教会の関心事だったラスコール(教会分裂)および古儀式派の問題とどう関連するでしょうか? 講演では、この教会裁判論を入り口として、ドストエフスキーのラスコール観を語ってみたいと思います。
講師プロフィール
望月哲男(もちづき・てつお) ロシア文学者、1951年静岡市生まれ。元北海道大学スラブ研究センター長。北海道大学名誉教授、現在日本ロシア文学会会長、国際ドストエフスキー協会(International Dostoevsky Society)副会長。
ドストエフスキー研究を出発点に、19世紀から現代の最先端の作家ソローキンに至るまで、近現代のロシア文学の研究・翻訳に精力的に携わってきた。また北海道大学スラブ研究センターを拠点に、数々の国際シンポジウムなどを手がけ、世界的なロシア文学研究者ネットワークの構築に貢献、いくつもの共同研究プロジェクトのリーダーを務めてきた。最近は古典の翻訳にも意欲を示し、ドストエフスキー、トルストイ、プーシキンなどの清新かつ正確な新訳が高く評価されている。新訳『アンナ・カレーニナ』(光文社古典新訳文庫)は、ロシア科学アカデミー「プーシキンスキー・ドーム」が制定した「最優秀ロシア文学翻訳賞」(2010年度)を授与された。
主催:科学研究費 基盤研究(A)25243002「越境と変容―グローバル化時代におけるスラヴ・ユーラシア研究の超域的枠組みを求めて」
共催:東京大学文学部スラヴ語スラヴ文学研究室・現代文芸論研究室
問い合わせ先:スラヴ語スラヴ文学研究室 03-5841-3847
会場地図:

日本ロシア文学会会長
三谷惠子
三谷惠子
ロシア文学会会費について
(正会員向け)
(2020年8月28日)会費等振込先
(郵便振替の場合)
口座記号・番号:00100-7-6507
加入者名:日本ロシア文学会
(銀行振込の場合)
銀行名:ゆうちょ銀行
金融機関コード:9900
店番:019
店名:〇一九(ゼロイチキュウ)
預金種目:当座
口座番号:0006507
日本ロシア文学事務局
日本ロシア文学会事務局
Сектретариат ЯАР
〔書記〕
〒060-0809
札幌市北区北9条西7丁目
〒060-0809
札幌市北区北9条西7丁目
北海道大学
スラブ・ユーラシア研究センター
安達大輔研究室内
スラブ・ユーラシア研究センター
安達大輔研究室内
〔庶務会計〕
〒102-8554
東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学外国語学部
秋山真一研究室内
E-mail(共通):
yaar@yaar.jpn.org
yaar@yaar.jpn.org
学会誌バックナンバー
学会員 1冊1000円
非学会員 1冊3000円
(2004年2月-2010年5月)は
こちらからご覧頂けます。
用語委員会編(1996年10月)