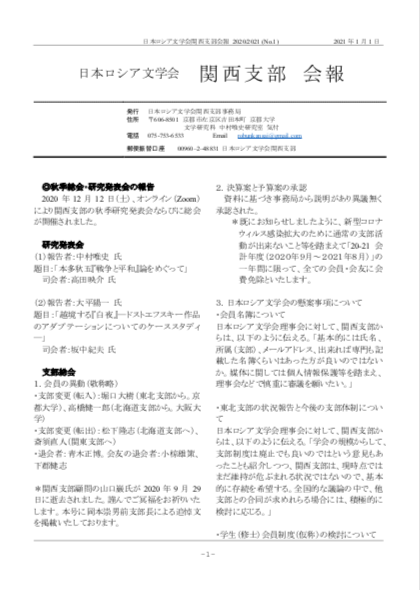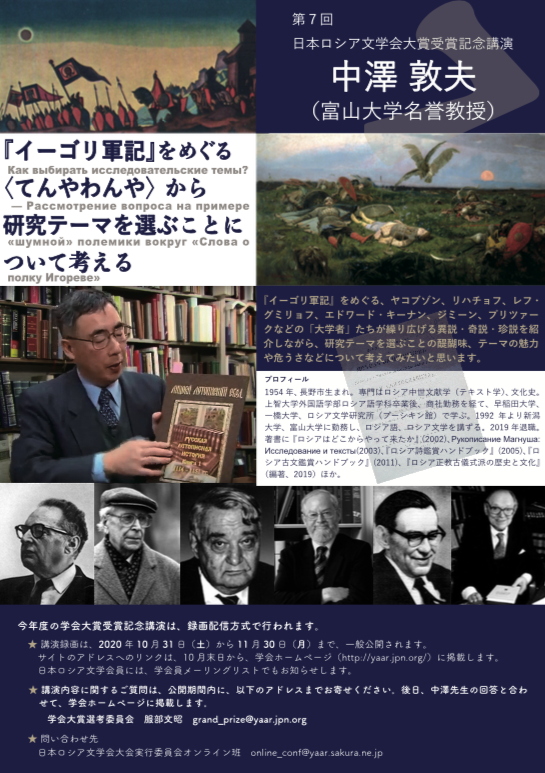カテゴリ:研究会・ワークショップ
日本18世紀ロシア研究会 第10回総会・研究発表会
日本18世紀ロシア研究会 第10回総会・研究発表会
農奴劇場(1775-1797)を中心に」
12:55 -- 13:45 長縄光男
そしてゲルツェン」
-------------------------------------------------------
 l.u-tokyo.ac.jp
l.u-tokyo.ac.jp子どものバイリンガル・ロシア語と日本語 -- 課題 と 展望
子どものバイリンガル・ロシア語と日本語 --- 課題 と 展望 ---
テーマとした講演,研究発表,ディスカッションを開催いたします.
第1部では,日本のバイリンガル教育研究の第1人者であり,継承語教育に関して多くの
著作,講演等を行っておられる中島和子先生をお招きし,講演とフロアーからの質問に
答えていただく機会を設けます.
また,会全体を通じて,この問題の現状を理解し,焦眉の課題へのよりよい解決策を探り,
今後,日本における継承ロシア語教育がより豊かに発展することをめざして,フロアーと
共に考えていきたいと思います.
どうぞ奮ってご参加ください.
---------------------------------------------------------------------------
(東京都八王子市丹木町1-236)
1)講 演
2)全国ロシア語補習校の紹介
1)「日本におけるロシア語話者「移民」‐子どもの継承ロシア語教育への展望:
保護者への意識調査」
2)「日本在住・ロシア語話者家庭の子弟におけるロシア語の教育とその継承」
3)「よりよい教科書を求めて」
1)過去の経験と蓄積から -- すべきこととしてはいけないこと
2)まとめと展望
自由討論(-18:00)
〒192-8577 東京都八王子市丹木町1 - 236 創価大学
Tel: 042-691-2211
お問い合わせ
大阪大学大学院言語文化研究科
M.A.カザケーヴィチ(margarit
 lang.osaka-u.ac.jp)
lang.osaka-u.ac.jp)参加希望の方は2012年9月15日までに上記までご連絡ください.当日参加も可能です.
外国語担当教員セミナーおよび高等学校韓国語中国語教師研修
2012年外国語担当教員セミナーおよび高等学校韓国語中国語教師研修
(『外国語学習のめやす2012』監修:カリフォルニア大学サンディエゴ校教授)
より詳しく考えるまたとないチャンスです。
戦争のメモリー・スケープ
国際研究集会「移民と亡命からみた20世紀ロシア文学」
基盤研究(B)「辺境と異境 -- 非中心におけるロシア文化の比較研究」
平成24年度国際研究集会
Русская литература ХХ века в аспекте миграции и эмиграции
日時: 2012年7月14日(土)
プログラム
1920-1930-х годов
 hotmail.com)
hotmail.com)「辺境と異境 -- 非中心におけるロシア文化の比較研究」事務局
亡命と移動の視点から見たロシア
ロシア語週間
НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
29 ноября ? 4 декабря 2010 года (Япония)
29 ноября
Для просмотра и прослушивания набрать в Интернете адресwww.vks.rosnou.ru
15:00 - 16:30 по токийскому времени
Круглый стол?Информационно-коммуникативные технологии в
преподавании русского языка?.
1. Антропова М.Ю., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой русского языка и общего языкознания РосНОУ - ?Русский язык ? и мы: обучение деловому общению как эффективный путь к взаимопониманию? (с презентацией).
2. Ковалева Н.А., доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка МГГУ им. М.А. Шолохова - ?Письма русских классиков в лингвосоциокультурном аспекте?.
3. Николенко Е.Ю., кандидат филологических наук, доцент кафедры РКИ филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова ? ?Как учат русскому языку в Московском университете (Презентация учебного комплекса ?Золотое кольцо?).
4. Палкин Е.А., кандидат физико-математических наук, профессор, проректор РосНОУ, лауреат государственной премии - ?Русский язык в системе современного профессионального образования? (на примере подготовки будущих инженеров).
16:45 - 17:20 по токийскому времени
Читательская конференция(ответы издателей (издательство ?Русский язык? и др.), а также авторов учебных пособий на вопросы участников).
30 ноября
Для просмотра и прослушивания набрать в Интернете адресwww.vks.rosnou.ru
15:00 - 16:30 по токийскому времени
Семинарповышения квалификации преподавателей-русистов, включающего в себя презентацию современных российских образовательных программ.
В рамках семинара состоится встреча с известными специалистами по русскому языку, авторами новых инновационных методик обучения
(Т.В. Васильева, доктор филологических наук, профессор, зав. каф. МГТУ ?Станкин? - лексикографичекие средства в РКИ;
И.В. Курбатова, кандидат пед. наук, доцент (Московская государственная юридическая академия) ? биоадекватные учебники и др.).
Участникам семинара будут вручены сертификаты повышения квалификации преподавателей-русистов.
Для просмотра и прослушивания набрать в Интернете адресwww.vks.rosnou.ru
17:30 - 19:00 по токийскому времени
Круглый стол?Русский язык в Японии. История и современность?
(С российской стороны принимают участие преподаватели русского языка, работавшие в Японии, ученые-японисты, историки, журналисты.).
Мастер-классы
1. Ковалева Н.А. ?Экскурсия как составляющая программы обучения русскому языку. Экскурсия по Чеховским местам. (Из опыта работы кафедры русского языка МГГУ им. М.А. Шолохова)
2. Николенко Е.Ю. ?Новое в методике преподавания русской грамматике? (Из опыта работы преподавателя МГУ им. М.В.Ломоносова)
1 декабря
19:00
Всех преподавателей-русистов и специалистов по русскому языку приглашаем в Посольство РФ
на церемонию открытия Недели русского языка.
С уважением
Фесюн Андрей Григорьевич,
представитель Россотрудничества в Японии
e-mail:japan@rusintercenter.ru
亡命と芸術―異境のロシア文化
Эмиграция и художественноетворчество- Русская культура на чужбине-「亡命と芸術―異境のロシア文化」
11月19日(金)
会場:同志社大学今出川キャンパス博遠館1F会議室
セッション1(使用言語:日本語)
13:00-13:45
報告:ЦУКАДАЦутому塚田力(北海道大学)
「1950年の中国イリ地区におけるロシア系住民に対する文化活動」
Культурная работа, проводившаяся в 1950 г. среди русского населения округа Или (КНР)
司会:САМИЦУ Синъити佐光伸一(北海道大学)
13:45-14:30
報告:МОТИДЗУКИЦунэко望月恒子(北海道大学)
Гайто Газданов, писатель "незамеченного поколения"
「見落とされた世代」の作家、ガイト・ガズダーノフ
司会:МИЯГАВАКинуё宮川絹代(東京大学)
セッション2(使用言語:ロシア語)
司会:Ирина МЕЛЬНИКОВАイリーナ・メーリニコヴァ(同志社大学)
14:45-15:30
報告:ИСАХАЯЮити諫早勇一(同志社大学)
Гражданская война и исход с точкизрения писателя-эмигранта Набокова
亡命作家ナボコフの目から見た内戦と脱出
15:30-16:15
Мария МАЛИКОВАマリヤ・マリコヴァ
(ロシア科学アカデミーロシア文学研究所/北海道大学スラブ研究センター)
Визуальное и телесное в русскойавтобиографической традиции: Набоков и Розанов
ロシア自伝文学の伝統におけるビジュアルなものと身体的なもの:ナボコフとローザノフ
セッション3(使用言語:ロシア語)
司会:МОТИДЗУКИЦунэко望月恒子(北海道大学)
16:30-17:15
Ирина МЕЛЬНИКОВАイリーナ・メーリニコヴァ(同志社大学)
"Тайны Востока" - ориентальные мотивы в творчестве эмигрантов и образ "загадочной России"
《東洋の神秘》 - 亡命者の創作における東洋的モチーフと、「謎のロシア」のイメージ
17:15-18:00
報告:АидаСУЛЕЙМЕНОВАアイーダ・スレイメノヴァ(極東国立総合大学/国際日本文化センター)
Япония глазами русских поэтов-иммигрантов (случаи Николая иВенедикта Матвеевых, МихаилаЩербакова и Виктории Янковской)".
ロシア亡命者が見た日本 - ニコライ&ベネディクト・マトヴェーエフ、ミハイル・シチェルバコフ、ヴィクトリア・ヤンコフスカヤを例として
懇親会
11月20日(土)
会場:同志社大学今出川キャンパス博遠館1F会議室(午前の部)
講演1(使用言語:ロシア語)
10:00-12:00
ЛИ Янлен李延齢(チチハル大学)
Литература русскихэмигрантов в Китае
中国におけるロシア亡命者の文学
司会:МОТИДЗУКИЦунэко望月恒子(北海道大学)
昼食12:00-13:00
会場:同志社大学今出川キャンパス尋真館Z6号(午後の部)
講演2(使用言語:ロシア語)
13:00-14:30
Наталья НУСИНОВАナタリア・ヌシノヴァ(映画芸術科学研究所)
Образ России в кинематографе эмигрантов как основа для формирования русского мифа на Западе
亡命者の映画におけるロシアのイメージ ―西側におけるロシア神話形成の基盤―
司会:Ирина МЕЛЬНИКОВАイリーナ・メーリニコヴァ(同志社大学)
14:30-16:00ワークショップ(使用言語:ロシア語)
映画上映
司会:Наталья НУСИНОВАナタリア・ヌシノヴァ(映画芸術科学研究所)
Кино русских эмигрантов в 1920-30-е годы
1920-1930年代 のロシア亡命者の映画
主催
・平成21年~平成24年度科学研究補助金(B)「辺境と異境 - 非中心におけるロシア文化の比較研究」(研究代表者:望月恒子)
・平成20年~平成23年度科学研究補助金(B)「音楽・演劇・映画の世界における「ロシア」イメージの形成に寄与した亡命者の研究」(研究代表者:イリーナ・メーリニコワ)
後援
・グローバルCOE「境界研究の拠点形成―スラブ・ユーラシアと世界」(拠点リーダー:岩下明裕)
ワークショップ「モダリティ研究と言語教育」のお知らせ
神奈川大学共同研究奨励助成プロジェクト
統語論的アプローチと語用論的アプローチによるモダリティの対照研究
モダリティ・プロジェクト ワークショップ2010
――モダリティ研究と言語教育――
日時:2010年7月24日(土)
会場:神奈川大学 横浜キャンパス1号館 804
来聴歓迎 参加無料 事前申込不要
総合司会 富谷玲子(神奈川大学)
10:30 開会挨拶 佐藤裕美(神奈川大学)
10:40-12:30 第一部「モダリティ研究の意義」
「文法形式に見られる話者の関わり」 砂川有里子(筑波大学)
「談話から見た推量的モダリティの呼応:
その動機付けと日本語教育への応用の可能性」
アンドレイ・ベケシュ(リブリャナ大学)
第一部総括 武内道子(神奈川大学名誉教授)
休憩
13:30-17:50 第二部「モダリティと言語教育」
13:30-15:00 「てしまう」のモダリティ性と日本語教育における課題
黒沢晶子(山形大学)
推量形式に関する日韓対照研究―韓国語教育の観点から―
文彰鶴(神奈川大学)
推量モダリティの文脈依存性に関する日中対照研究 彭国躍(神奈川大学)
15:00-15:20 休憩
15:20-16:30(つづき)
ロシア語におけるモダリティとアスペクト
―日露対照研究とロシア語教育の観点から― 堤正典(神奈川大学)
英語法助動詞の諸相と英語教育 久保野雅史/佐藤裕美(神奈川大学)
第二部総括 富谷玲子(神奈川大学)
16:30-17:30 ディスカッション
17:30 閉会挨拶
懇親会(1号館802) 18:00開始(20:00終了)
-----------------------------------------------------------------------
問い合わせ:
神奈川大学言語研究センター
〒221-8686 横浜市神奈川区六角橋3-27-1
(東急東横線白楽駅徒歩13分)電話045-481-5661 (内線4470 / 4471)
日本ロシア語教育研究会主催サマーセミナーのお知らせ
日本ロシア語教育研究会主催サマーゼミナー「教える力をパワーアップする」を下記の要領
で開催いたします。
どうぞみなさま奮ってご参加ください。
日本ロシア語教育研究会主催サマーセミナー「教える力をパワーアップする」
日本ロシア語教育研究会は、教える力が1日でパワーアップするようなサマーセミナーを
開催します。セミナーは、CEFRという大きな枠組みに根ざした教育実践についてのお話、
秋からの授業を刷新するリスニングとリーディングの指導法の実演、ロシア語教師の
教室での悩みと誤りを共有し答えを探るワークショップの「開店」という充実した内容と
なっています。講師の方々のフィールドもロシア語、ドイツ語、英語教育と多彩です。
ロシア語以外の言語を教えてらっしゃる先生方、将来、ロシア語を教えたいと
思っている学生諸君、どなたでも歓迎いたします。高等学校の先生方もふるって
ご参加ください。
またセミナー後、語学教育について、多方面からざっくばらんに話し合えるよう、
懇親会も企画しています。こちらへの参加もお待ちしています。
*また,お知り合いの方や職場等でお声かけをお願いできれば幸いです.
ポスターは以下のサイトからダウンロードできます.
http://www.rokyoken.com/page/oshirase.htm#summer2010
----------------------------------------------------------------------
● 日時:8月21日(土)12:00 -- 18:00
● 場所:大阪大学豊中キャンパス 言語文化研究科2階大会議室
● プログラム:
12:00 - 挨拶
12:10 - 13:40 「ワークショップ“ШОП” ( школа опытных преподавателей ) 」
マルガリータ・カザケービッチ氏(大阪大学世界言語研究センター招聘教員)
13:40 - 13:55 質疑応答
13:40 - 13:55 休憩
14:10 - 15:40 「CEFRの理念をどう実現するか?‐ポートフォリオというしかけ‐」
境一三氏 (慶応義塾大学外国語教育センター所長、ドイツ語・ 外国語教育学)
15:40 - 15:55 質疑応答
15:55 - 16:10 休憩
16:10 - 18:00 「しっかりとした基礎力を育成するためのリスニングとリーディングを
中心とした効果的な指導法‐TPR・ポーズ・スラッシュの活用‐」
鈴木寿一氏(京都外国語大学英米語学科教授、英語教育学)
18:30 - 懇親会
●ポスターhttp://www.rokyoken.com/page/oshirase.htm#summer2010
●参加費 3000円 ※懇親会代は別途
●申し込み締め切り:8月14日(土) ※当日参加も可能
●参加申し込み&問い合わせ先:日本ロシア語教育研究会事務局
rokyoken2jimu@yahoo.co.jp
なお本会の活動につきましては下記のホームページをご覧ください。
http://www.rokyoken.com
●交通アクセス http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/
●キャンパスマップ http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/toyonaka.html
多数の皆様のご参加をお待ちしております。
日本ロシア語教育研究会事務局 伊藤美和子,三浦由香利
rokyoken2jimu@yahoo.co.jp
----------------------------------------------------------------------
●講師からのメッセージ
本セミナーの講師の一人であるカザケービッチ先生からセミナー参加者の方々へ
次のようなメッセージが届いています。どうぞ遠慮なく、メールでお返事ください。
Дорогие коллеги! Если у вас есть конкретные преподавательские проблемы,
если вы хотите посоветоваться о том, как лучше организовать работу в классе,
если вы чувствуете: что-то у вас ещё не получается, если вы поняли свою
методическую ошибку и хотите предостеречь от неё своих коллег -- пишите об
этом до конца июля по адресу margo@world-lang.osaka-u.ac.jp
Таким образом мы сможем сделать наш семинар максимально практическим и
полезным!
----------------------------------------------------------------------
三谷惠子
ロシア文学会会費について
(正会員向け)
(2020年8月28日)日本ロシア文学事務局
日本ロシア文学会事務局
〒060-0809
札幌市北区北9条西7丁目
スラブ・ユーラシア研究センター
安達大輔研究室内
yaar@yaar.jpn.org
(2004年2月-2010年5月)は
こちらからご覧頂けます。